News

If you're unsure what to give as a Father's Day...
Father's Day is the third Sunday in June. This day comes around every year, and many people are probably wondering what to give this year. Alcohol and ties are nice,...
If you're unsure what to give as a Father's Day...
Father's Day is the third Sunday in June. This day comes around every year, and many people are probably wondering what to give this year. Alcohol and ties are nice,...

When is Mother's Day this year? Stylish and pra...
When is Mother's Day in 2025? Mother's Day in 2025 is Sunday, May 11th Mother's Day is celebrated on the second Sunday of May every year. In 2025, Mother's Day...
When is Mother's Day this year? Stylish and pra...
When is Mother's Day in 2025? Mother's Day in 2025 is Sunday, May 11th Mother's Day is celebrated on the second Sunday of May every year. In 2025, Mother's Day...

What is a tenugui? A clear explanation of the d...
Have you ever wondered, "What is the difference between a tenugui and a handkerchief?" Recently, a variety of tenugui have been sold, from traditional designs to modern ones, and more...
What is a tenugui? A clear explanation of the d...
Have you ever wondered, "What is the difference between a tenugui and a handkerchief?" Recently, a variety of tenugui have been sold, from traditional designs to modern ones, and more...

What is Kanreki? The reason for celebrating 60 ...
Kanreki is a major turning point in life. However, many people may wonder, "Why 60?" and "Why do we wear red chanchanko?" This article will explain in detail the meaning...
What is Kanreki? The reason for celebrating 60 ...
Kanreki is a major turning point in life. However, many people may wonder, "Why 60?" and "Why do we wear red chanchanko?" This article will explain in detail the meaning...
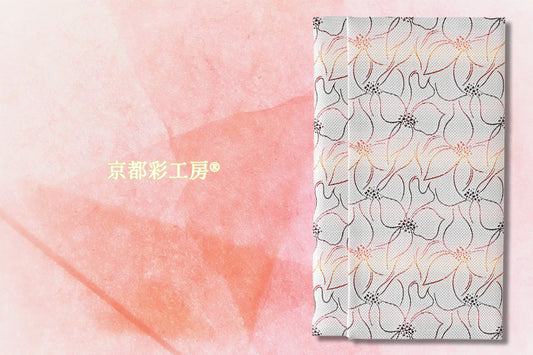
Choosing the Color of Fukusa and Furoshiki for ...
1. Points to consider when choosing a furoshiki or cloth for women For women, fukusa and furoshiki can also be used to express elegance and style. By choosing designs and...
Choosing the Color of Fukusa and Furoshiki for ...
1. Points to consider when choosing a furoshiki or cloth for women For women, fukusa and furoshiki can also be used to express elegance and style. By choosing designs and...

For men! A guide to choosing the colors of fuku...
1. Points to consider when choosing a furoshiki or cloth for men Fukusa and furoshiki are often used in formal occasions, especially for men, such as weddings, funerals, and business...
For men! A guide to choosing the colors of fuku...
1. Points to consider when choosing a furoshiki or cloth for men Fukusa and furoshiki are often used in formal occasions, especially for men, such as weddings, funerals, and business...